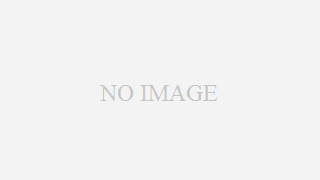 物語り・その20
物語り・その20 物語り その20
「生命の液体」として「水」という溶媒は非常に広範な用途を持つ物質である。生命という劇場で主役と端役の両方を演じる驚くべき能力を持つとともに、もう一つ重要な点は、水が液体として存在する温度範囲で、化学反応の速度が生物が損傷の原因(放射線、微細なスケールでの条件の変化、惑星規模での変動など)に対処しなければならない頻度と良好に一致している。しかも、水が宇宙に大量に存在しているため、その物理的特性は生物に適しているだけでなく、より広い宇宙の物理法則を考えると、新たな進化の実験が始まる際の惑星で利用できる一般的な溶媒になる可能性が示唆される。