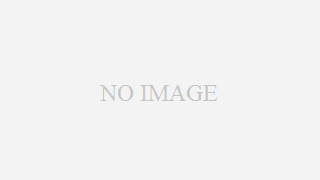 物語り・その30
物語り・その30 物語り その30
「ペイル・ブルー・ドット」と形容される地球は、広大な宇宙の中では微小な存在であり、そこに生きている私たちは更に極微な存在である。しかし、私たちは宇宙のガス、塵から生まれ進化し、現在の文明の高度な段階に到達した。宇宙開闢インフレーションは真空の相転移から生じたと言われているが、何もない状態、「無」と言ってもよいものから、自らを認識し自らを高めようとする自律体が生まれてきたのである。まさに奇跡である。次世代を担う若い人たちには、人類、つまり私たち自身の存在、そして私たち自身が築き上げてきたものに意味を見い出し、その上でさらに一歩進んでいって欲しいと切に願っている。