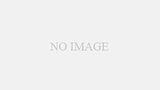第七部 人類が築いてきた文明のあらすじと到達点
第3章 第二の時代:農業と都市
農業が生んだ都市と分業
我々の祖先は、約10万年間、会話を交わしながら狩猟や採集に従事する生活を続けた後、劇的な変化を経験した。
- 『農業』を発明したのである。
これにより、人類自体と社会全体が根本的に変化した。この第二の時代が始まったのはおおよそ1万年前である。
その時点での地球上の総人口は約400万人で、現在のロサンゼルスの人口よりわずかに多い程度であった。前の9万年間において、我々の祖先が人口を4~5倍増やすことがやっとであった。それは極めて微弱な成長率であり、当時の人類が非常に脆弱な存在であったことを示している。

農業は、言語と同様に技術であり、それもまた、言語と同じく他の多くの進歩を促進した。
- その一つが『都市』の誕生である。
農業を行うためには一箇所に定住する必要があったため、都市が発展した。これは全く新しい試みであった。最古の都市の一部であるチャタル・ヒュユク、エリコ、テル・アブ・フレイラなどは、水源と肥沃な農地へのアクセスが容易な川沿いに作られ、そこには市場、住居、寺院などが設置されていた。人類が阿片を使ったり、サイコロを用いた賭け事を始めたり、化粧を施したり、金の装飾品を身に着け始めたのもこの時代である。
都市は交易やアイデアの交換を活性化させた一方、我々人類を完全かつ決定的に定住化させた。住居は永続的に居住するためのものであった。我々は堤防や高台を築き、地形を変え、塀や柵を建てた。さらに、後で訪れることができるように、死者を埋葬した場所に特別な標識を設置した。これら多くの要素により、我々の祖先の移動性は抑えられた。もはや後戻りすることはできなかった。
- 農業と共にもたらされた二つ目の技術的進歩は、『分業』である。その重要性は直観的には理解し難いかもしれないが、分業は人類史上最も重要なマイルストーンの一つとなった。
分業により、自分の生存のために必要な全ての作業を自分一人で行う必要がなくなり、特定のタスクに特化することが可能となった。これは効率化につながり、爆発的な経済成長を実現する基盤となった。「分業化」は、「交易」や「技術の進歩」と共に、全体の富を増やすために労働量を増やすことなく行える三つの手段(経済学ではこれを『フリーランチ』(注229)と呼ぶ)の一つであった。
(注229)「フリーランチ」とは、客を引き寄せるために無料の食事を提供し、収益を他のサービスから得る販売手法のことを指す。1870年代から1920年代の文献にその存在が記されている。これはアメリカの各地のサルーンで一般的な慣習であった。これらの店では、最低でも1杯の飲物を購入すると「無料の」食事が提供された。食事の質は粗末なものから手の込んだものまで様々で、通常、1杯の飲み物の価格よりも価値が高かった。サルーンの経営者は、ほとんどの客が2杯以上の飲み物を注文し、また将来も再訪することを期待していた。
- 農業が直接分業を引き起こしたわけではない。農業は都市を生み出し、都市が分業を引き起こしたのである。
その理由は、分業が最も効果的に機能するのは大量の人々が狭い範囲に集まって生活している時であるからだ。隣人から遠く離れて孤立して生活する農民は特定の分野に特化して生活することが困難であり、必然的に様々な作業をこなすようになる(しかし、その全てに精通するまでには至らない)。
最古の都市から得られた考古学的証拠は、第二の時代の始まりから既に多種多様な職業が存在していたことを示している。人類が多数集まって共同生活を送るようになると、専門化がもたらす莫大な経済的恩恵を享受することが可能になった。
分業を開始すると、人間同士の協力は任意的なものから必須的なものへと変わった。経済学者レオナルド・リードが著した著名なエッセイ『私は鉛筆』では、一本の鉛筆の製造方法を始めから終わりまで全て理解している者はいないにも関わらず、何百もの分野で働く何千もの人々が、お互いに面会することなく、それぞれが鉛筆製造の一部を担当し、鉛筆が絶えず製造され続けていると述べられている。我々が今日手にする全ての物は分業の成果であり、分業がなければ我々は滅びるであろう。
- 都市が生み出した重要なもう一つの技術は、組織的な戦争で使用される『武器』である。
武器は、富を集中させる都市の防衛を必要とする状況で生まれた技術である。初期の都市は壁によって防護されており、その壁の構築には大量の労力とコストが必要であった。これは、都市が攻撃の対象となるリスクが十分に存在したことを示している。
- 農業の発展と都市の出現により、人類は歴史上初めて、『土地を所有』することになった。
人類は本質的に縄張り行動を示す種であるため、土地の所有権を主張するエリアが存在していたことは間違いないだろう。しかしながら、領土の境界線が明確に設定されていた考古学的証拠は、第二の時代初期に初めて出現する。哲学者ジャン=ジャック・ルソーはこれを近代の始まりと見なし、次のように述べている。「一人の人間が『特定の土地を自分のものだ』と主張し、他の人々がそれを受け入れる瞬間が、政治社会の真の創設の瞬間であった」と。
格差社会への突入
- 農業の発展と個々の土地所有の増加により、第一の時代に見られた経済的平等は終焉を迎えた。能力、生まれ、運といった自然に生じる不平等さが、『富の不平等な蓄積』につながるようになったのである。
近代的な意味での貨幣制度はこの時点ではまだ確立していなかったが、富という概念は明確に存在していた。人々は土地、家畜、穀物の貯蔵施設などを所有することができ、これらは無制限に蓄積できる資産であったため、人間はいくらでも豊かになれた。耕作できる土地や繁殖させられる牛など、そのころの資産は収入源となり、結果的に富は増大し続けた。この富は世代を超えて受け継がれ、蓄積され、複利的に増加した。
- そして、残念ながら、『奴隷制度』が始まったのも第二の時代だった。
富が存在しない、あるいは一時的にしか存在しない狩猟採集社会では、奴隷制度はほとんど意味をなさなかった。しかし、都市の出現、土地所有権の獲得、富の蓄積により、人間の所有欲が刺激され、それが奴隷制度の設立に繋がった。巨額の富を持っていてもなお更なる富を追い求める人々が存在するように、富への渇望には(少なくとも一部の人間において)限界がないようである。人権や個人の自由といった概念が存在しなかったこの時代において、奴隷制度は倫理的な問題を引き起こすものではなかった。その不道徳性が明確に認識されるようになったのは、文明が進歩したはるか後のことである。
時間の経過と共に、他の人々よりも多くの土地や資産を蓄積した者たちが出現した。社会が豊かになるにつれて複雑化し、貿易は進化し、技術は発展し、都市は拡大した。これらすべての要素が合わさることで、一人の人間が蓄積できる富の最大限度が上昇した。
しかしながら、農業革命は予想外の副作用をもたらした。
- 食料生産量が増大する一方で、食料の分配に問題が生じた。すなわち、人々に食料が行きわたらなくなったのである。
狩猟採集社会では考えられなかった事態だが、都市と農業の組み合わせにより、権力者が食料を渡すことで支配を維持する手段を生み出した。この方法は現代においても一部の地域で見られる。
- こうした状況の下、人々は『支配者』と『被支配者』に分かれるようになった。貴族や王族の出現もこの第二の時代の特徴である。
支配者はしばしば特定の商品や食料を独占し、被支配者がそれを使用することを禁止した。アステカ文明では、特定の花の香りを嗅ぐことさえも禁止されたと伝えられている。
自由と平等の緊張関係が明瞭になった時期は近代においてである。
歴史家ウィル・デュラントの見解によれば、人間は自由と平等を同時に享受することは不可能で、どちらか一方を選択しなければならない。自由を拡大すると不平等が増大し、一方で平等を追求するためには自由を犠牲にしなければならない。この自由と平等のバランスを求める取り組みは、今日まで続いている。
先述のとおり、
- 人類が進歩するための1つ目の必要条件は『想像力』であったと述べた(<物語り その26>)。
そして、2つ目に必要だったものは農業によってもたらされた。穀物を植え育て収穫するには、狩猟採集生活をしている間は全く無縁だった『計画力』が必要だったことから、
- 農業の発明は、『未来という概念』の発明でもあった。
これこそが、人類の進歩にとって必要な第二の条件であった。
第4章 第三の時代:文字と車輪
外部記憶としての文字
『火』を使って「食物が調理できる」ようになったことで私たちは『大きな脳』を獲得し、その脳が『言語』を生み出し、その言語によって私たちは「協調して働いたり」、「抽象的な思考をしたり」、「物語を作ったり」できるようになった。1万年前、『農業』は私たちを「定住させ」、その結果「都市が形成され」、「富が蓄積する」ようになった。都市は、経済成長と技術革新をもたらす「分業が発達する」のに最適な場だった。
そして、『第三の時代』はわずか5000年前、

- 現在のイラク南部に居住していた『シュメール人』が『文字』を発明したことで幕を開けた。
- エジプトや中国でも同時期に独立して文字が発明され、後に現在のメキシコでも独立して発明された。文字の出現は人類に革命をもたらした。
- 人間が一生の間に獲得した知識を、その人が亡くなった後も保存することが可能になった。知識は完全にコピーされ、世界中に運搬されるようになった。結果として、アイデアは人間の心の外で生存することが可能となった。
ところで、こうした利点のどれ1つとして、文字を発明する原動力だったわけではない。初期の文字はもともと、資産や取引を記録するために生み出されたのである。それがやがて、法的記録、法典、宗教にまつわる文言を書き記すのにも利用されるようになった。演劇や詩といった創作に使われるようになったのはさらに後のことである。
当然ながら、最初に文字を読むことができたのは地球上に暮らしていた1000万の人々のうちごく少数であった。文字の読み書きは、それにかかるコストが高かったため、広く普及しなかった。文字を読み書きする能力を獲得するためには大量の時間を投資する必要があった。また、情報を記録するメディアである『紙』は、当時のパピルス、粘土、大理石など、非常に高価なものであった。
- しかし、文字はその圧倒的な便利さからすぐに生活のあらゆる場面で利用されるようになり、その結果世界を変革した。もし文字という技術がなかったら、現代の世界はどのようなものになっていたであろうか。
- 文字は、人類史において極めて大きな転換点であった。第一の時代と第二の時代は先史時代に位置づけられ、歴史は5000年前の第三の時代から始まった。
しかし、プラトンの主張に従えば、文字を使うことは我々の記憶力を弱める一面を持っている。
- 火を使うことで消化の一部をアウトソーシングしたように、文字を使うことで我々は「記憶をアウトソーシング」しているのである。
文字が存在しなかった時代には、何かを知りたいと思った時、それを覚えておく以外に方法はなかった。古代史はその頃の人々が非常に優れた記憶力を持っていたことを示している。しかし、我々の記憶力が文字が発明された瞬間に衰えたわけではない。それはまだ本が一般的でなかったからである。しかし、現在ではほとんどの知識はGoogle検索で得られるため、我々の記憶力はこれから更に衰える可能性がある。
文字が法をつくり、車輪が人々へ広げた
ここまで考察してきた重要な技術と同様に、文字の出現の背後には、それを生み出しさらなる有効活用を可能にする新技術があった。
- その一つが、同じく5000年前頃に発明された『車輪』である。
車輪と文字は、ピーナツバターとジャムのように相性が良い。この二つが組み合わさることで商業は発展し、情報の流通が可能となり、人々の旅行が現実化した。文字ができたことにより、支配者は『法典』を作成することが可能となり、その法典を広範囲に行き渡らせることを可能にしたのは車輪であった。
初期の法典は非常に短く、支配者になるためには全ての法律を記憶しなければならないというルールを持つ文化も少なからずあった。「法の不知はこれを許さず」という格言はこの時代に生まれた。全ての法律が少数であったため、法律の不知を訴えることは許されなかったのである。我々は依然としてこの格言が正しいと信じているが、現実にはその逆であろう。法律が数百万ページに及ぶ現代社会では、法律の不知は適当な言い訳となり得るだろう。
- 約4000年前の『ウル・ナンム法典』をはじめとする初期の法典では、殺人、強盗、誘拐、強姦、偽証、暴行、所有地に対する様々な犯罪(隣人の土地を水没させたり、借りている畑を耕作するのを怠ったり、他人の畑で密かに耕作したりするなど)に対して、それぞれ罰則が定められていた。
- その数世紀後に成立した『ハンムラビ法典』では、これら全てが282の法律に纏められ、さらに契約の履行、製造物責任、相続についての法律が追加されている。
- 『貨幣』が登場したのも第三の時代である。
現代的な鋳造硬貨の出現は更に時代を経なければ見ることはできないが、金、銀、貝、塩などの形状の貨幣は第三の時代の早い段階から世界中に存在していた。金属はその価値が一般的に認識され、分割可能であり、耐久性があり、携行可能であったため、理想的な通貨と見なされていた。冶金技術は第三の時代の初期にすでに始まっており、人々は銅と錫を混ぜると、それぞれよりも優れた特性を持つ『青銅』ができることをすぐに学んだ。
文字、車輪、貨幣が世の中に同時に出現したことで、国家と帝国を作るための基本的な素材が整ったのである。
- ここで初めて、大規模な文明が世界中で同時に花開いた。強力で豊かで結束した国家が中国、インダス、メソポタミア、エジプト、中央アメリカに出現した。
これらの文明がほぼ同時に、しかも互いに遠く離れた場所で出現した理由は未だ解明されていない。文字の出現も同様である。なぜ5万年や2万年前に世界のどこかで文字や車輪、農業が発展しなかったのか、その理由は誰にも分からない。
それにせよ、
我々の祖先はこの時点で、「言語」、「想像力」、「分業」、「都市」、そして「未来に対する感覚」を手に入れていた。「文字」、「法典」、「車輪」、「契約書」、「貨幣」も揃っていた。
- これらが揃っていたことにより、我々は次の数千年にわたり技術を迅速に発展させることができたのである。
- 我々の世界は最近まで第三の時代であった。その間に『蒸気機関の開発』、『電力の利用』、『活字の発明』など多くの革新的な進歩はあったが、それらは言語や農業や文字のように人間の生存形態を根本から変えるものではなかった。
- 第三の時代に起きた主な革新は、革命的ではなく、進化的なものであったと言える。
それでも、それらが重要でなかったとは言えない。印刷は世界を劇的に変えた。しかし、それは我々がすでにできていたことを、より安価に、より速く行えるようにしただけであった。レオナルド・ダ・ヴィンチに複葉機の詳細な設計図を見せれば、彼も理解できただろう。
- 我々が真に新しい時代に進んだと考えるためには、我々の存在や生活を大幅に、永遠に変える何かが起きなければならない。我々の種としての進行方向や進化の軌跡を変える何かが必要である。
- そうして、我々を第四の時代へと進める物語は、第三の時代の最後の数世紀から始まるのであった。
図表
図324 テル・アブ・フレイラ
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「テル・アブ・フレイラ」
(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A9)
図325 シュメール人の都市国家
2022 世界の歴史まっぷ
(https://sekainorekisi.com/glossary/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB/)