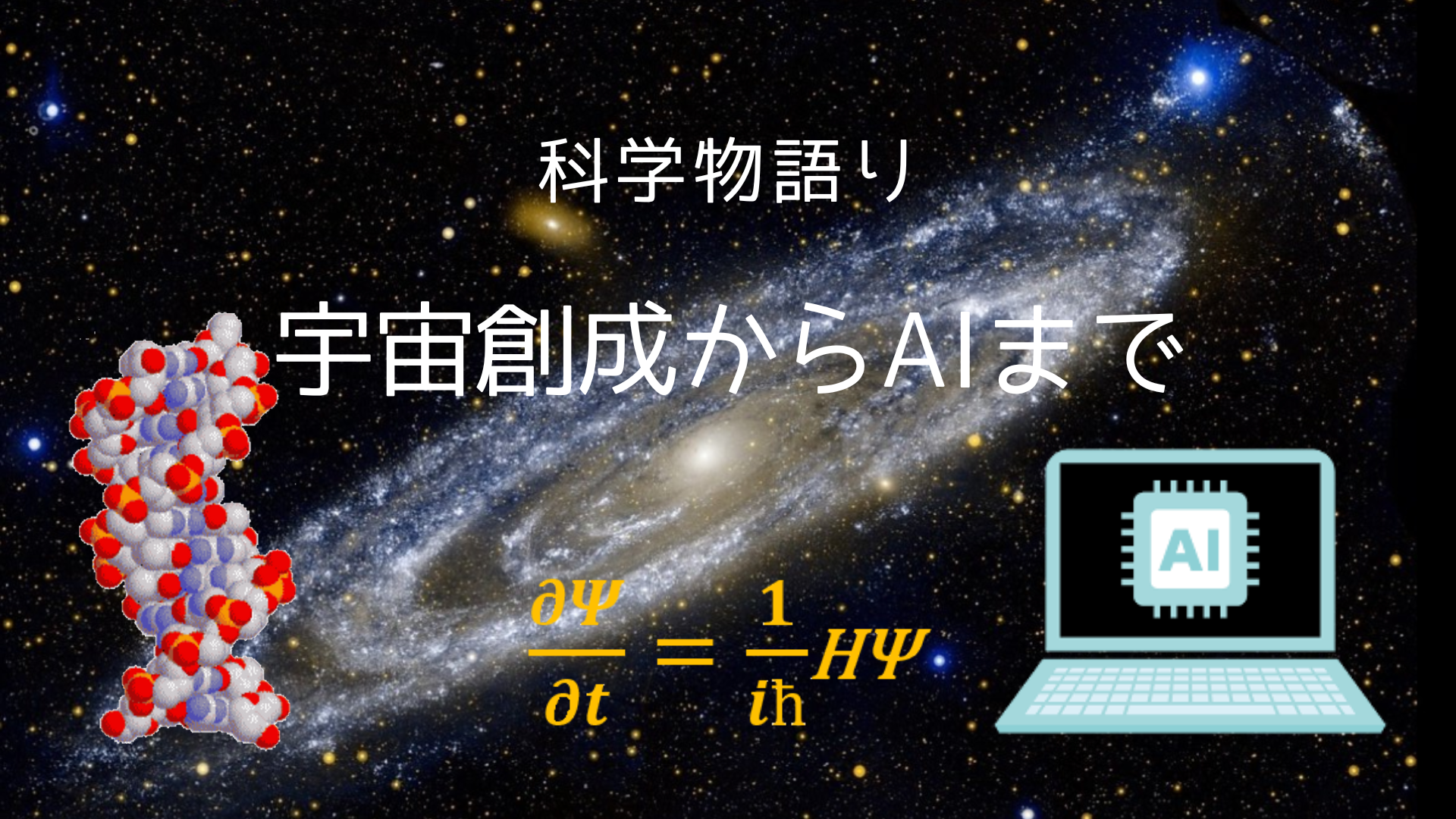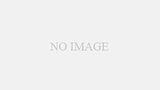本「物語り」は、これからの人類世界を担って行くべき若き少年少女の皆さんへの語りかけである。「現宇宙世界の成り立ちから地球の誕生、生命の誕生、進化、そして私たち人類の現在までの滔々とした道のり」、すなわち、科学者たちを中心に苦闘の末に明らかにされてきた偉大な成果であるが、それを皆さんが理解、再認識し、将来に向けて自分たちの進むべき道を考える際の因って立つ礎として活用されんことを期待しつつ書き連ねたものである。
なお、最初にお断わりしておかなければならないが、この物語りの各「部」に記載の内容は、参考文献欄に掲げた原著(翻訳版)を大いに参照しており、記述内容のオリジナル性はそれらの著書に帰すべきものである。むしろ、私が力を注いだのは、それぞれの原著が著わしたテーマを分かりやすく再構成しつつ時間軸に沿って繋げ、一つの「物語り」として編み上げた点にある。そのことによってわれわれの棲む世界の姿を幾ばくかでも見やすくすることができたのではないだろうか。この物語りが少しでもオリジナリティを有しているとすれば、この点にこそ認められるのではないかと考えている。
物語りは、「第一部 宇宙の誕生とその構成」から始まる。私たちの宇宙の起源となったのは、『ビッグバン』と呼ばれる壮大な爆発である。ただし、ビッグバンを引き起こした具体的な瞬間やその前に何が存在していたかについては、現在の科学では明確には分っていない。ここでは、われわれの存在する宇宙が約138億年前、誕生直後の約0.00000000000000000000000000000001秒(小数点以下に31個のゼロ)の間に「時空そのもの」が、光の速さを超える速度で
約10,000,000,000,000,000,000,000,000倍(10億京倍)に膨張したという驚くべき『インフレーション』の理論が提示され、その後、生成した宇宙の構成が語られる。恒星や惑星、そしてその表面に存在するすべての物体など、私たちが知っている(知覚できる)物質は全宇宙の約5%を占めるに過ぎず、27%は未知の何かである『ダークマター』、残りの68%はほとんどその性質が理解されていない『ダークエネルギー』である。このダークエネルギーこそが、宇宙の膨張を駆動していると考えられている。
続いては、「第二部 地球の誕生と原始進化」である。ここでは、「太陽系の誕生とその構造」に続いて「地球の誕生と原始進化」が語られる。地球には海水が存在し、表面の70%が海洋になるとともに40~38億年前からプレートテクトニクス(地震活動や火山活動など地球の表面近くで起こるいろいろな現象を『プレート』と呼ばれる厚さ数10kmの岩盤の運動で説明する学説)が作動し始めた。その沈み込みによって地球の内部に持ち込まれた水を媒介として海洋地殻が変質し、同時に安山岩質のマグマを生産しているという特徴が、『生命』という革新的な有機システムを地球に誕生させるきっかけを創り出したのである。
それを受けて「第三部 生命の誕生」では、生命の誕生は不連続的な発現ではなく、ある特定な環境下で連続的な現象の積分的な積み重ねから実現されたものであることが解明されつつあること、そしてそればかりでなく、生命が『エネルギーの流れ』に深く関係しているということが明かされる。すなわち、「エネルギーは生命の進化の要」であり、エネルギーを方程式に持ち込んで初めて生命進化の特質が理解できる。しかも、進化ばかりではなく、このエネルギーと生命の関係は生命の始まりにまで遡るのである。『生命』の根本的な特質、それは、たゆまず活動する惑星に生じた不均衡から必然的に現われたもの(『散逸構造』)なのである。生命がエネルギーの流れによって誕生し、『プロトン勾配』が細胞の出現の鍵を握っていたのである。
続いて、「第四部 生命の進化」が語られる。まず、「生命を育む仕組みとその歴史」が説かれ、その後、シアノバクテリアによる「酸素の出現」という大変動を経て『真核生物』が登場し『多細胞生物』の出現に結び付いたこと、さらには「凍りついた地球(『全球凍結』)」を経験することによる動物の誕生・進化が語られる。『節足動物』をはじめとする現在に至るまでの動物の「門」の多数が初めて登場したのは、約5億3000万年前から5億2000万年前という比較的短い期間に集中している。これは『カンブリア爆発』と称されているが、この現象と地殻全体に対する地軸の位置の変化である『真の極移動』との関連性が語られる。その後、動物の多様化と酸素濃度との相関を調べつつ動物の発展、すなわち「動物の陸上進出」と「節足動物の時代」に言及される。しかし、動物の発展は順調には続かず、2億5200万年前のペルム紀末の酸素濃度の低下・欠乏と硫酸塩還元細菌が作り出した硫化水素によって全種の90%が絶滅したと推定されるという『大絶滅』に見舞われた。しかも、三畳紀という長い時代を通じて酸素濃度が現代より低く、この低酸素状態、特に大量絶滅後の低酸素状態が生物の新しい形態の多様性を増加させ、カンブリア紀以来最多となる新しい形態が生まれた。三畳紀はまさしく、動物にとっては重要なカンブリア紀に匹敵すると認識されており、生物が急速に多様化したこの時期を『三畳紀爆発』と呼んでいる。この酸素不足の状況から生まれた新種の動物のほとんどが酸素危機に対する高い適応能力を持つ呼吸器系を有していた。陸上では、厳しい環境の中から二つの新しいグループ、すなわち『哺乳類』と『恐竜』が登場した。前者は獣弓類に取って代わり、後者は世界を支配することとなった。なお、初期の恐竜の『二足歩行体制』は三畳紀中期の低酸素環境への反応として進化、すなわち、二足歩行の姿勢をとることで『キャリアの制約』による呼吸の制約を克服したのである。つまり、三畳紀の低酸素環境が触発要因となり、この新体制が形成され、結果として恐竜が誕生し、低酸素世界における恐竜の覇権が確立したのである。一方、中生代の海洋は温暖化の影響で時間とともに変化していったが、当時を象徴する『アンモナイト類』と『イノセラムス類』は、状況が許せば今でも生存していた可能性がある。しかし、約6500万年前、チクシュルーブ小惑星(最大で直径10~15キロメートル)が地球に衝突し、恐竜をはじめ当時地球上に存在した種の半分以上が急激に絶滅した。メキシコのユカタン半島で発見された大型の『衝突クレーター(チクシュルーブ・クレーター)』はこの時代に形成されたものである。しかし、当該絶滅は小惑星の衝突という単発のイベントだけが誘因ではなく、当該衝突の前にデカン高原での噴火で大気中に多量のメタン、二酸化炭素、二酸化硫黄などの温室効果ガスが放出されたため地球の気候と環境が激変し、大量絶滅が誘発されていたことが判明している。デカントラップが世界を弱らせ、隕石がとどめを刺したのである。一方、哺乳類については、その多様化、最も目立つ変化である大型化は恐竜が絶滅した直後に起きた。その後の27万年間で、哺乳類は多様化するとともに体も大きくなっていったのである。ただし、本当の意味で大型と呼べる哺乳動物が出現したのは、約5500万年前になってからであった。当時、地球の温度が急速に上昇し、世界中に森林が広がり、南北両方の極地付近にも樹木が生い茂った。これは、哺乳類の多様性の大幅な拡大を後押しした可能性がある。さらに、鳥類については、その始まりは約1億5000万年前に出現した『始祖鳥』である。しかし、鳥類の起源については主に二つの見解、すなわち、鳥類が恐竜以外の双弓類(爬虫類に似た動物)から進化したという考え方と、鳥類が直接恐竜から進化したとする見解があるものの、過去10年の間に主に中国で1億3000万年前~1億1500万年前の白亜紀の岩石から発見された多数の鳥の化石から「恐竜起源説」が確定的となった。
最後に、私たち自身、人類の進化の系統樹を観る。現在、かなり解明されており、私たちが属する科『ヒト科』の歴史はおそらく600万年前~500万年前に始まったと見られる。以降、ヒト科の生物は九種が確認されているが、更新世以前の初期のヒト科生物で最も重要なのは、道具を使用する能力からその名がつけられた『ホモ・ハビリス(「器用なヒト」の意)』である。我々と同じホモ属としては最古の種で、約250万年前に出現した。約150万年前にはホモ・ハビリスから『ホモ・エレクトス』が生まれ、そしてホモ・エレクトスから最終的に我々『ホモ・サピエンス』が派生したが、それは約20万年前にエレクトスの直系の子孫として生まれたか、あるいは『ホモ・ハイデルベルゲンシス』という中間の段階を経て進化したかのどちらかと考えられている。ホモ・サピエンスはさらにいくつもの変種へと細分化した。『ネアンデルタール人』を変種の一つとして扱う研究者もいれば、「ホモ・ネアンデルターレンシス」という別の種と解釈する者もいるが、最新の証拠によると、現生人類と我々の現在のDNAが出現する前に、人類とネアンデルタール人の系統はすでに分岐していたとされている。したがって、ネアンデルタール人が我々から生まれたのでもなく、その逆でもない。どちらも、すでに絶滅した共通の祖先から進化したので、その祖先はどちらの種とも異なる存在であった。化石記録によると、我々の種(より原始的な『ホモ・サピエンス』と区別するために『現生人類』と呼ばれることもある)の中で、現時点で知られている最古の仲間は、19万5000年前に現在のエチオピアにあたる地域で生活していた。しかし間もなく、この集団はアフリカ大陸の遥か南へと旅立ち、それから北へと進み、アフリカからユーラシア大陸に渡り、次第に世界中に広がった。その結果、この放浪者たちは自らを他の仲間から遮断し、自分たちが辿り着いたそれぞれの環境に適応していくことになった。
以上、第三部と第四部では、生命がどのように誕生し、進化してきたのかを詳しく見てきた。そして、時間や空間を超えて観察される生命の複雑性や多様性に目を向けると、生命が物理的な作用とは基本的に異なる何かを示しているかのように感じられることもある。非生物的な世界の構造は予測可能で、単純な原理に基づいて形成されているように見える一方で、生命はそのような原理を超越して進化していると想像しがちである。しかし、事実として、生命体という集合体はそのあらゆるレベルで、「物理法則」が特定の解を生命に提示しているのである。結果は常に予測可能とは言えないが、無限ではない。微粒子から生物集団の規模まで、物理法則が作用しているレベルに関わらず、結果は多様ではあるが無限にはないのである。
そこで少し寄り道をして、「第五部 生命進化の物理法則」に触れてみたいと思う。数々の研究者による優れた研究成果から得られた証拠を集積することで、物理的原理が生命の構造の各レベルで進化の範囲をどの程度限定しているかを示すことが可能である。そして、その見解の基盤となっているのは単純な視点、「進化とは環境が有機体の構成要素を選択するフィルターの役割を果たす作用であり、その有機体では複雑に作用し合う物理法則が繁殖の成功を可能にするように最適化される」という点である。ここでの「環境」には、嵐から捕食者の食欲まで、繁殖を妨害する可能性のある全ての要因が含まれている。要は、「進化」とは遺伝物質として暗号化された物理的原理がもたらす驚異的で興味深い相互作用に他ならない。そして、数式で表現される物理法則の数が限られているということは、進化の結果もまた有限であり、同時に普遍的であることを意味するのである。さらに、物理学と生物学の間に密接な関係があるならば、仮に地球外生命が存在すると考えると、それらは地球の生命に驚くほど似ている可能性があり、陸生生物は、進化における一つの実験で生まれた特異な存在というよりも、宇宙全体の生命の大部分にとってのテンプレートになるかもしれない。また、少なくとも我々の世界では、「『細胞』を持つことが生物の特徴の一つである」というのは避けられない視点である。細胞を持つことにより、単に凝集された機構が誕生しただけではなく、進化過程において多種多様な選択と淘汰が可能となったからである。その意味において、『細胞』と『進化』は深い結びつきを持っている。そこで、それぞれの細胞の膜とその周囲を詳しく見てみると、自己複製が可能な地球上のすべての生命体には『膜』が存在し、これは内部の全てを包み込む『袋の役割』を果たしている。この膜は単なるシート状の化合物ではなく、微小な袋のような構造をしており、膜を形成する分子は驚くべき特性と単純な美しさを持つ。その膜の内部に収まっているのが「頭と尻尾を持つ分子」であり、尻尾は炭素原子が互いに連なった長鎖で『疎水性』を持つのに対して、頭部は『親水性』で水に溶けやすい。つまり、一つの分子は一端が疎水性、もう一端が親水性という二つの極端な性質を併せ持つことになる。この分子を水に加えると、異なる分子の尾部が互いに向き合い、頭部が水の方向を向くように配置される。これらの分子が形成する『二層構造』は自発的に形成され、尾部がその疎水性に基づいて水を避ける一方で、水へ向いた頭部はその親水性を発揮する。この脂質膜には他にも驚くべき特徴を持つ。それは水中を漂う無限のシートを形成するのではなく、エネルギー、すなわり『表面張力』を最小化するように、この膜は外部からの刺激を受けずに自然に球状になり、内部に液体を閉じ込める。これにより、細胞の一つの区画が現れる。脂質の配列や脂質が球を形成しやすい特性の背後には、『イオン相互作用』という分子間に働く物理的原理と、『エネルギーを最小限』に抑える傾向があり、それが長い分子の連鎖を『細胞の袋』へと導くのである。これなども物理法則が特定の解を生命に提示している典型的な例である。
ここまでは、過去数十億年にわたって繰り広げられた地球の変化の本質と、地球上の生命の進化を見てきた。次の部「第六部 人類の出現と進化」では、「過去500万年で類人猿の祖先からヒトが進化した過程」と「過去10万年で人類が潜在能力を高め、世界中に拡散した経緯」、さらに「第七部 人類が築いてきた文明のあらすじと到達点」では、「この一万年間で次々と誕生した文明」、「過去1000年間に起きた商業化、産業化、グローバル化の新たな動向」、そして「過去一世紀間で、この壮大な起源の物語を人類がどのように理解するようになったか」について検証する。
人類の起源については、『ヒト族(ホミニン)』と呼ばれる進化の樹の一部門が存在する。これは霊長類という広範な動物群の一部を構成し、最も近い生きた種は『チンパンジー』であり、ヒトとチンパンジーの分岐は約1300万年前から始まり、恐らく700万年前まで交雑が続いていたことが推測されている。しかし、最終的には双方の進化の歴史は分岐し、一方では現在の『チンパンジー』と『ボノボ』が出現し、もう一方では『ホミニン』のいくつかの異なる種が出現した。私たち自身の種、『ホモ・サピエンス』はその一つの枝分かれにすぎない。では、「ホミニンの進化」はどのように進展したのだろうか。その進化の主要なステップはすべて『東アフリカ』で生じたという点が特筆すべきである。この時期、「ヒマラヤ山脈の造山」、「インドネシア海路の封鎖」、そして特に「『東アフリカ地溝帯』の高い尾根の隆起」という地殻変動プロセスの結果が、東アフリカを乾燥させた。「地溝帯」の出現は、この地域の生態系を変化させる過程で、気候だけでなく地形も変えた。東アフリカは一面の熱帯林に覆われた平坦な土地から、高原と深い谷がある険しい山岳地帯に変貌し、植生は雲霧林からサバンナ、そして砂漠の低木帯まで多様化した。東アフリカが長期間にわたり乾燥化し、森林の生息環境を断片化し、サバンナに置き換えた結果、樹上生活をする霊長類からホミニンへと分岐が生じた。しかし、これが唯一の要因ではなかった。大地溝帯は地殻変動によって極めて複雑化し、多様な地形が隣接する移行帯を形成した。これには森林と草原、尾根、急な断崖、丘陵、高原と平原、谷、そして大地溝帯の谷底に形成された深い淡水湖などが含まれる。この地域はモザイク環境と呼ばれ、ホミニンに対して多様な食糧供給源と生活資源、そして機会を提供した。約400万年前には、『アウストラロピテクス(南の猿)』が出現し、華奢で長身の体型など、現生人類と共通する形質を持つようになった。これは頭蓋骨がまだ原始的な形状であったにも関わらずであり、また、二足歩行も得意とするようになっていた。『アウストラロピテクス・アファレンシス(アファール猿人)』が現存する化石からよく知られている。その中にはアワッシュ川流域で約320万年前に生きていた女性の驚くほど完全な骨格があり、『ルーシー』として知られている。約200万年前、アウストラロピテクス属のホミニンの種は全て絶滅し、私たち自身の属である『ヒト属(ホモ属)』が出現した。『ホモ・ハビリス(器用な人)』は、それ以前の猿人に似た華奢な体型を保ちつつ、脳だけはわずかに大きかった。体と脳のサイズが大幅に増大し、生活様式が大きく変わったのは、『ホモ・エレクトス』が約200万年前に出現してからであった。ホモ・エレクトスは頭蓋骨以下の身体構造が現生人類と解剖学的に非常に似ており、長距離走行の適応や物を投げる能力を持つ肩の構造を持っていた。成長が遅く、長い子供時代を送ること、高度な社会的行動をするなど、その他のヒトとの共通点もあったとされている。ホモ・エレクトスは、狩猟採集生活を送り、また「火」を扱うことのできた最初のヒト属のホミニンであったと推定されている。火は暖を取るためだけではなく、食物を調理するためにも使用されていたと考えられる。彼らは筏を用いて広い水域を渡る能力も持っていた可能性がある。
一方、ホミニンの活動する大地である地球は、おおよそ260万年前、現在の『氷河期の世(エポック)』へと突入した。この時期には、『ミランコヴィッチ・サイクル』として知られる地球の公転軌道と自転軸の傾きが規則的に変化し、氷期と間氷期が交互に繰り返されてきた。東アフリカは前進する氷床そのものと直接対面するには南北両極から遠すぎたが、それでもこの宇宙的な周期によって大きな影響を受けた。特に、地球が太陽を周回する軌道が周期的に楕円形に伸びる「離心率周期」により、東アフリカの気候は大きく変動する時代がもたらされた。極端な変動が見られるこれらの局面それぞれに、地軸の拍動も加速し、気候は非常に乾燥した状態と湿潤な状態の間で揺れ動いた。先に述べたように、東アフリカは地中から上昇してくるマントル・プルームによって隆起し、その結果地殻が引き伸ばされて最終的に亀裂が入り、断層が形成された。その結果生じた大地溝帯の地形は、大量の地殻が沈み込んだ平坦な谷底と、その両側にそびえ立つ尾根を特徴とする。特に300万年前からは、谷底には孤立した広い盆地が数多く形成され、湿度が充分にある時期には、これらが湖となる。これらの深い湖は重要である。それはホミニンにとって、乾季の間でも安定した水源となったからである。しかしながら、多くの湖は一時的なものであり、気候が変化するにつれて、湖は時代と共に現れ、また消えていった。リフト(大地が両側に引っ張られることによって生じた谷間のこと)のある地形は、高地と谷底で明確に異なる気候条件を生み出す。雨はリフトの高い断崖と火山の山頂付近に降り、それがはるかに暑く蒸発率の高い谷底に点在する湖に流れ込む。これは、大地溝帯の湖が降水量と蒸発量のバランスに大きく左右され、わずかな気候変化でもその水位が大幅に、そして急速に変化することを意味する。世界各地の湖やアフリカの他の地域の湖と比べても、その変動幅は大きい。地域の気候のわずかな変化が、生きるのに欠かせないこれらの水域の水位を非常に大きく上下させるため、これらの湖は『アンプ湖』と呼ばれている。微弱な信号を増幅させるハイファイのアンプのような役目を果たすからである。そして、地溝帯を作り出す長期にまたがる地殻変動の傾向と、地球の気候の変動、人類の進化に直接、劇的な影響を及ぼした居住環境の急速な変化とを結びつけた重要なつなぎ目が、これらの特殊な「アンプ湖」なのである。過去数百万年にわたり、東アフリカの環境はおおむね非常に乾燥していたが、この一般的な状態にもときおり、気候が大いに湿潤な時期と、逆に再びひどく乾燥する時期があり、極端な変動期が訪れた。このような気候の変動は約80万年周期で生じ、その間、アンプ湖は緩んだ電球のようにちらついては消える。この変動に伴い、水源、植生、食糧の状況も大きく変動し、これが人類の祖先にも深刻な影響を及ぼした。急速に変化する状況は、多芸で適応力のあるホミニンをより生き延びさせることになり、こうしてより大きな脳と多くの知能を進化させたのである。そのように気候が極端に変動した最も直近の三つの時代は、270万年前から250万年前、190万年前から170万年前、100万年前から90万年前に訪れた。化石記録を調査した科学者たちは、ホミニンの新種(ヒト属)が、しばしば脳容量の増大と関連して、現れたタイミングや絶滅した時期が、これらの乾湿変動の時代と一致する傾向があることを発見した。例えば、人類の進化においてきわめて重要な出来事の一つは、190万年前から170万年前の変動期に生じていた。地溝帯にある7つの主要な湖盆(水をたたえて湖となった部分)は、繰り返し水が溜まっては干上がっていた。ホミニンの様々な種がその最盛期を迎え、脳容量が大幅に増大したホモ・エレクトスもこの時期に出現した。結論として、判明しているヒト属の15種のうち、12種がこの3つの変動期に初めて登場した。さらに、各段階の石器技術の発展と普及-オルドワン、アシュール、ムスティエ-もまた、気候変動が極端になる離心率の時期に呼応していた。そして変動の時代は人類の進化を左右しただけでなく、ヒト属のいくつかの種に誕生の地を離れて『ユーラシア大陸へ移住』させた原動力であったとも考えられている。約180万年前になると、ホモ・エレクトスはアフリカ全土に広がり、その後、何度かの移住の波を経てこの大陸を離れ、ユーラシア全土に拡散した。この種は約200万年間存在した。ホモ・エレクトスは約80万年前に『ホモ・ハイデルベルゲンシス(ハイデルベルク人)』を生み出し、その後25万年前にヨーロッパでは『ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)』が、アジアでは『デニソワ人』が進化した。これらの古人類がヒトとは別種であるかどうかについては、専門家の間で見解が分かれている。解剖学的に見ると、『現生人類』と定義される『ホモ・サピエンス』は、東アフリカで約30万年から20万年前に初めて出現した。したがって、『現生人類』としての私たちの種が誕生してからは、ホモ・エレクトスの存在期間の10分の一ほどしか時間が経過していないのである。
約10万年前から、地球の軌道配置が特定の位置に整うようになった。地軸の傾きの影響で、北半球の夏は楕円軌道上で地球が太陽から最も離れている時期と重なり始め、それは北方の夏がより低温になることを意味した。冬に降った雪は融けず、積雪は増加し続けた。地球が次の氷期に入ると、北方の氷床は増大し、南方へ拡大していった。そこで、この最も最近の氷期、そしてその結果としての世界の海水準の低下が、人類が世界各地に広がるための決定的な機会を提供した。一方、世界規模の遺伝子研究からもたらされた結果として、何よりも驚くべきことは、「ヒトという種がきわめて均一である点」という事実である。髪や肌の色、あるいは頭蓋の形状には地域的な差異が存在するものの、現在世界に生息する75億人の人間間の遺伝的多様性は非常に乏しいのである。しかも、ヒトの遺伝的多様性はアフリカ内で最も豊かであることから、全ての人間がアフリカから始まったこと、そしてその出生地から広がったことはやはり明らかであろう。私たちは全て「アフリカの子供」であるが、誰もがその発祥の地に留まることはなかった。おおよそ六万年前、私たちの祖先はアフリカから各地へ散り始めたのである。さらに、遺伝学的研究からは、現在世界各地に分布する人類は、複数回の移住の波ではなく、「アフリカからの一度きりの脱出劇の子孫であり、その初期の移住者はおそらくわずか数千人だった」と示唆されているのである。
現生人類である『ホモ・サピエンス』は、気候が湿潤となりアラビア半島が緑化した時期に初めてその地へ進出したと考えられている。彼らがシナイ半島を北に向かって縦断したか、あるいはバブ・エル・マンデブ海峡を筏で渡ったのかは明らかでない。ユーラシア大陸へと広がり始めるにつれて、我々の祖先は早くからアフリカを離れていたヒト属の他の種と接触した可能性がある。現生人類は中東では『ネアンデルタール人』と若干ながら交雑したので、彼らのDNAの痕跡を受け継ぎ、世界のその他の地域へ移り住む中でそれを携えていった。また、中央アジアを通過した際には、『デニソワ人』と呼ばれる絶滅した謎のヒト属の種との間でさらなる交雑が発生したとも考えられている。より古いヒト属の種である『ホモ・エレクトス』はアフリカを約200万年前に離れ、中国とインドネシアにまで到達していた。しかし、人類がアジア全体に広がった時代には既に絶滅していた。アラビア半島から中国のユーラシア南部海岸沿いまでの人類の拡散は、年間で見れば500メートル以下の割合で進行していた。それでも結果的に、人類は地球を占有したのである。私たちヒト属の近縁種であるネアンデルタール人とデニソワ人は絶滅していった。彼らが狩猟や殺害で絶滅したというよりは、単にヒトとの競争に敗れた可能性が高い。あるいは氷河期のピーク時に生じた厳しい環境に耐えられなかった可能性もある。最後のネアンデルタール人は4万年前から2万4000年前に姿を消し、私たちは地球上に生き残った唯一のヒト属となった。アフリカから移出してから5万年以内に、人類は南極大陸を除く全ての大陸に定住し、地球上で最も広範囲に生息する動物種となった。火の使用、衣服の作製、道具の製造といった技術を身につけることで、サバンナの類人猿から始まった私たちは、熱帯からツンドラまであらゆる気候帯で生活することが可能となった。世界各地への勢力拡大が、最終氷期の極寒の気候の最中に生じたという事実は、多くの人々を驚かせるかもしれない。しかし、実際にはこの氷河期の環境こそが、人類の大規模な拡散を可能にしたのである。北方で拡大した氷床が海から大量の水を取り込み、それによって海面が低下し、大陸棚の大部分が露出したためである。陸地を歩いてインドネシアまで行き、狭い海峡を渡ってオーストラリアへ、そして最も重要なこととしてベーリング陸橋に沿ってアメリカ大陸まで人々が渡ることができたのは、まさにこの氷河期の条件が整ったからである。
『解剖学的現生人類(モダン・ヒューマン)』は約20万年ほど前に登場しているが、私たちの祖先の行動が現代的になったのは、10万年前から5万年前の間からだった。その頃、人類は現在の私たちと同様の言語と認識能力を具え、社会集団を形成し、道具を作り、火を使う技術を習得していた。彼らは死者を丁寧に埋葬し、衣服を作り、表現豊かな芸術作品を生み出すようになり、洞窟壁画のほか骨や石の彫刻に自分たちの姿や、周囲の自然界を描くようになった。彼らは熟練した狩人であり、魚を獲り、食用の植物を広範囲にわたって収集し、穀物を石臼で粉にするという作業すら始めていた。前述したように、現生人類は約6万年前にアフリカから出発し、地球のあらゆる場所へと拡散した。しかし、農業と定住生活への最初の永続的な一歩が踏みだされたのは約1万1000年前であり、これは『新石器革命』と呼ばれる過程であった。北アメリカの氷床は急速に縮小していたが、地中海東部の肥沃な三日月地帯で最初の作物が栽培化され、そのすぐのちに中国北部の黄河流域でも栽培化が始まったころには、カナダの半分以上がまだ氷に覆われていた。その後数千年の間に、世界の他の地域でも祖先たちは同じ過程を始め、農業は北アフリカのサハラ砂漠の南縁部のサヘル地域、メソアメリカ、南アメリカのアンデス=アマゾン地域、北アメリカ東部の森林地帯、ニューギニアにも現れたのである。最終氷期を10万年間狩猟採集の生活を送りながら生き抜いた後、地球が温暖化するにつれて、世界の様々な場所にいた人々は『農業と文明』という道を歩み始め、それが人類を恒久的に変えたのである。文明の誕生は、『植物の栽培』だけに依存していたわけではない。『野生動物の家畜化』もまた重要な役割を果たしていた。いったん家畜化されれば、それ以外の産物や労働力も継続的に得られるが、こうした利用は野生動物が相手では到底できないもので、畜産はまったく新しい資源をもたらすのである。このことは『二次産物革命』と呼ばれている。また、大型動物の家畜化は、狩猟採集社会には手に入らなかった別の重要な資源も提供した。『輸送と牽引のための役畜』としての筋力である。家畜の牽引力を利用することで、農耕民は鍬や掘り棒などの小さな農耕具を使う人力による農業から、『犂(からすき)』の利用へ移行することができた。そのうえ、馬が引く二輪戦車が前二千年紀にはユーラシアで『戦争に革命』を起こした。後に、より大型で力の強い馬が品種改良によって生まれ騎乗が可能になると、騎馬兵が最も効率のよい戦争の武器となったのである。動物の筋力の利用は、人間社会の潜在能力を大幅に拡大した。異なる環境にまたがる遠距離の交易や旅行は、馬やラバ、ラクダによって可能となった。また、力がありながらも足の遅い牛や水牛のような動物は、四輪荷車や犂を引く牽引力となった。そして、五世紀に中国で『頸帯式馬具(わらび型)』が発明されると、馬もまた牽引に利用できるようになった。これは、北ヨーロッパの重い土地で中世に農業生産性を大幅に向上させる進歩であった。これらの動物を家畜化し、人の筋力を補完させたことは、人類がエネルギー源を大規模に活用するようになった最初の段階であった。畜力は6000年以上にわたって、産業革命が始まり化石燃料が導入されるまで、文明の原動力として絶大な地位を保持したのである。産業革命が起きると、石炭火力の蒸気機関が列車と船を動かし始め、後には内燃機関が、原油から精製した液体燃料を駆動力として用い、広大な距離を驚異的な速度で移動することを可能にした。
ここまでで、われわれ人類が拠って立つところの「宇宙の誕生とその構成」、「太陽系の誕生とその構造」、「地球の原始進化」、およびそれに続く「生命の誕生」、「生命の進化-生命を育む仕組みとその歴史・酸素の出現・真核生物の登場・多細胞生物の出現・動物の誕生と進化・動物の多様化と酸素濃度・動物の陸上進出・大絶滅と三畳紀爆発・低酸素世界における恐竜の覇権・恐竜の絶滅・哺乳類の時代・鳥類の時代」という宇宙・天文・地学・生物学的な進化を俯瞰し、「人類の出現と進化」にまで言及してきた。最後に、「第七部 人類が築いてきた文明のあらすじと到達点」では文明論的な観点からわれわれ人類の現在の立ち位置をまとめてみよう。
人類史という大きな枠組みの中で捉えると、実は過去5000年の間に変わったことはそれほど多くない。5000年前の人々と同様に、我々にも家族があり、学校や政府、宗教や戦争、平和が存在する。出産の祝いや死の悼みも変わらず続いている。スポーツ、結婚式、ダンス、宝石、タトゥー、ファッション、ゴシップ、社会階級、さらには恐怖や愛、喜び、幸せ、歓喜等、これらは全ての文化で普遍的に見られ、永遠に我々と共にある。このように考えると、人類は基本的にはあまり変わっていない。驚くべきことに、我々は祖先と非常に似ている。時代背景が変わっても、我々はわずかしか変化していない。それどころか、真の変化は人類史の中でたった3度しか起きなかったと考えてよいのである。これらの変化は全て技術によってもたらされた。特定の一つの技術ではなく、互いに関連する一連の技術が、根本的に、持続的に、そして生物学的にまで我々を変えたのである。これら3つの大きな変化が全てであり、それらに基づいて、4つ目の変化として『AI』が出現しつつある。
まずはじめ、遥か昔、人類史における最大のエポックの一つ、そして最初の大きな転換点が訪れた。それが『言語の発明』である。そこで、このエポックまで遡り、その意義について考えてみることにしよう。『火』は「史上初の多機能技術」であった。火は光源となり、動物が火を恐れることから安全を提供した。また、火は持ち運び可能で、寒い地域にも暖を取りながら移動することが可能であった。しかし、火の最大の功績は、『食物を加熱調理』できるようにしたことである。なぜこの功績が最も重要であったのかというと、加熱調理により、摂取できるカロリーが大幅に増大したからである。つまり、火は私たちの体内で行われる消化プロセスの一部を『アウトソーシング』する道を開いたというわけである。生の食材を摂取しても大部分が未消化のまま体内を通過する。そのため、現代の人間が生存に必要なカロリーを生の食材だけでまかなうことは困難である。では、こうして得た大量のカロリーを、私たちの祖先は何に使ったのだろうか。答えは「脳」である。彼らは、これらのエネルギーを投入し、比類なき複雑さを持つ脳を進化させた。結果として人間は短期間で、ゴリラやチンパンジーが持つ3倍のニューロンを獲得し、ぜいたくにも総消費カロリーの20%をこの高度化した脳を支えるためだけに使っている。生存という観点からは、これはかなり大胆な賭けだったが、その賭けがめでたく報われ、私たちはもう1つの新たな技術である『言語』の創造に至ったのである。言語はまさに大きな飛躍であり、歴史家ウィル・デュラントによれば、「言語が私たちを人間にした」。そのようなわけで、「火」こそが、私たちと『技術』が今も織りなす長い長い物語の出発点だったということになり、そのおかげで生まれた一層強大な技術である「言語」は、私たちが『情報を交換』することを可能にした。さらに、「言語」は人間が持つ特殊能力の1つともいえる『協力』を可能にした。言語を持たないヒトが1ダース集まってもマンモス1頭には太刀打ちできないが、言語を使って協力し合えれば、彼らは強大な力を持つようになる。私たちの大脳は言語を生み出し、言語を通じて思考することで大脳がさらに発展するという好循環も生まれた。言葉を使わなければ達成できない特定の思考パターンが存在するからである。言葉は基本的に考えを表す記号であり、話すという技術がなければ、複雑な思考の組み合わせや変化を処理する方法が不明瞭である。言語はさらにもう一つの大きな贈り物を与えてくれた。それは、『物語』である。「物語」とは私たちが進歩するために最初に必要だった「想像力」に形を与えるものであり、人間に最も重要な要素である。
我々の祖先は、約10万年間、会話を交わしながら狩猟や採集に従事する生活を続けた(『第一の時代』)後、劇的な変化を経験した。『農業』を発明したのである。これにより、人類自体と社会全体が根本的に変化した。この『第二の時代』が始まったのはおおよそ1万年前である。農業は、言語と同様に技術であり、それもまた、言語と同じく他の多くの進歩を促進した。その一つが『都市』の誕生である。農業を行うためには一箇所に定住する必要があったため、都市が発展した。これは全く新しい試みであった。農業と共にもたらされた二つ目の技術的進歩は、『分業』である。その重要性は直観的には理解し難いかもしれないが、分業は人類史上最も重要なマイルストーンの一つとなった。分業により、自分の生存のために必要な全ての作業を自分一人で行う必要がなくなり、特定のタスクに特化することが可能となった。これは効率化につながり、爆発的な経済成長を実現する基盤となった。「分業化」は、「交易」や「技術の進歩」と共に、全体の富を増やすために労働量を増やすことなく行える三つの手段の一つであった。農業が直接分業を引き起こしたわけではない。農業は都市を生み出し、都市が分業を引き起こしたのである。都市が生み出した重要なもう一つの技術は、組織的な戦争で使用される『武器』である。武器は、富を集中させる都市の防衛を必要とする状況で生まれた技術である。初期の都市は壁によって防護されており、その壁の構築には大量の労力とコストが必要であった。これは、都市が攻撃の対象となるリスクが十分に存在したことを示している。農業の発展と都市の出現により、人類は歴史上初めて、『土地を所有』することになった。人類は本質的に縄張り行動を示す種であるため、土地の所有権を主張するエリアが存在していたことは間違いないだろう。しかしながら、領土の境界線が明確に設定されていた考古学的証拠は、第二の時代初期に初めて出現する。哲学者ジャン=ジャック・ルソーはこれを近代の始まりと見なし、次のように述べている。「一人の人間が『特定の土地を自分のものだ』と主張し、他の人々がそれを受け入れる瞬間が、政治社会の真の創設の瞬間であった」と。農業の発展と個々の土地所有の増加により、第一の時代に見られた経済的平等は終焉を迎えた。能力、生まれ、運といった自然に生じる不平等さが、『富の不平等な蓄積』につながるようになったのである。狩猟採集社会では考えられなかった事態だが、都市と農業の組み合わせにより、権力者が食料を渡すことで支配を維持する手段を生み出した。こうした状況の下、人々は『支配者』と『被支配者』に分かれるようになった。貴族や王族の出現もこの第二の時代の特徴である。
人類が進歩するための1つ目の必要条件は『想像力』であったと述べた。そして、2つ目に必要だったものは農業によってもたらされた。穀物を植え育て収穫するには、狩猟採集生活をしている間は全く無縁だった『計画力』が必要だったことから、農業の発明は、『未来という概念』の発明でもあった。これこそが、人類の進歩にとって必要な第二の条件であった。そして、『第三の時代』はわずか5000年前、現在のイラク南部に居住していた『シュメール人』が『文字』を発明したことで幕を開けた。エジプトや中国でも同時期に独立して文字が発明され、後に現在のメキシコでも独立して発明された。文字の出現は人類に革命をもたらした。人間が一生の間に獲得した知識を、その人が亡くなった後も保存することが可能になった。知識は完全にコピーされ、世界中に運搬されるようになった。結果として、アイデアは人間の心の外で生存することが可能となった。文字は、人類史において極めて大きな転換点であった。第一の時代と第二の時代は先史時代に位置づけられ、「歴史は5000年前の第三の時代から始まった」。ここまで考察してきた重要な技術と同様に、文字の出現の背後には、それを生み出しさらなる有効活用を可能にする新技術があった。その一つが、同じく5000年前頃に発明された『車輪』である。車輪と文字は、ピーナツバターとジャムのように相性が良い。この二つが組み合わさることで商業は発展し、情報の流通が可能となり、人々の旅行が現実化した。文字ができたことにより、支配者は『法典』を作成することが可能となり、その法典を広範囲に行き渡らせることを可能にしたのは車輪であった。『貨幣』が登場したのも第三の時代である。現代的な鋳造硬貨の出現は更に時代を経なければ見ることはできないが、金、銀、貝、塩などの形状の貨幣は第三の時代の早い段階から世界中に存在していた。金属はその価値が一般的に認識され、分割可能であり、耐久性があり、携行可能であったため、理想的な通貨と見なされていた。冶金技術は第三の時代の初期にすでに始まっており、人々は銅と錫を混ぜると、それぞれよりも優れた特性を持つ『青銅』ができることをすぐに学んだ。「文字、車輪、貨幣」が世の中に同時に出現したことで、「国家と帝国」を作るための基本的な素材が整ったのである。ここで初めて、大規模な文明が世界中で同時に花開いた。強力で豊かで結束した国家が中国、インダス、メソポタミア、エジプト、中央アメリカに出現した。これらの文明がほぼ同時に、しかも互いに遠く離れた場所で出現した理由は未だ解明されていない。文字の出現も同様である。なぜ5万年や2万年前に世界のどこかで文字や車輪、農業が発展しなかったのか、その理由は誰にも分からない。いずれにせよ、我々の祖先はこの時点で、「言語」、「想像力」、「分業」、「都市」、そして「未来に対する感覚」を手に入れていた。「文字」、「法典」、「車輪」、「契約書」、「貨幣」も揃っていた。これらが揃っていたことにより、我々は次の数千年にわたり技術を迅速に発展させることができたのである。我々の世界は最近まで第三の時代であった。その間に『蒸気機関の開発』、『電力の利用』、『活字の発明』など多くの革新的な進歩はあったが、それらは言語や農業や文字のように人間の生存形態を根本から変えるものではなかった。第三の時代に起きた主な革新は、革命的ではなく、進化的なものであったと言える。我々が真に新しい時代に進んだと考えるためには、「我々の存在や生活を大幅に、永遠に変える何かが起きなければならない」。「我々の種としての進行方向や進化の軌跡を変える何かが必要である」。そうして、我々を『第四の時代』へと進める物語は、第三の時代の最後の数世紀から始まるのであった。
1620年には、フランシス・ベーコンが『ノヴム・オルガヌム-新機関』(桂寿一訳、岩波文庫)を出版した。これこそ、今日私たちが『科学的方法』と称するものの始まりであったと言われている。ベーコンは、自分の手を使って自然を研究すること、そしてその過程で注意深く観察し、データを記録することの重要性を強調した。そのように得られたデータに基づいてのみ、結論を導出することが可能であると主張した。これは、今日私たちが考える科学的方法と完全に一致するわけではないが、「観察を通じた知識獲得の体系化」と「その方法論を提案」したという点でベーコンの功績は大きかった。世界を一変させる、偉大な考えだったといってよい。それまでの人類の進歩は断続的で非効率的であり、例えば「車輪の再発明」は単なる比喩ではなく、車輪は実際、何度も発明された。科学的方法を利用すれば、一人が集めたデータやその結論を別の人が使用し、その知識を更に発展させることが可能になる。つまり、私たちの科学的知識は複利的に成長するようになり、それが現在の私たちが存在する理由である。今日の科学的方法は「知識を獲得するための普遍的な手法」と「得られた知識を他人が検証し、さらにその上に積み重ねることができる形で公開する方法」によって構成されている。この方法が適用されるのは、測定可能な物体や現象のみである。ここで重要なのは、客観的に測定できることである。客観的な測定の結果なら、他の研究者が再現できる(あるいは再現できないことが分かる)からである。科学的方法には、安価で信頼性のある印刷技術が必要であった。そのため、この時代より前には科学が進展しなかったのかもしれない。印刷コストが低下するにつれて、科学の進歩は加速していった。他人の仕事をもとに、段階的に改良を加えていく。ニュートンはこのプロセスのことを、「巨人の肩の上に立つ」と表現した。なにより、印刷機の発明と普及によってリテラシーが向上し、情報の自由な流通が可能となった。これが、17世紀に現代が始まる主な契機となった。
科学的方法によって技術開発が加速度的に進行するようになると、全ての技術に共通する奇妙な特性が明確となってきた。『技術の性能はある期間でみると、一定間隔で繰り返し倍増し続けている』、というものである。技術が持つこの深遠かつ不可思議な性質が発見されたのは、わずか半世紀前のことであった。インテル社の創設者の1人ゴードン・ムーアが、集積回路に乗せられるトランジスタの数が約2年おきに2倍になるという興味深い事実に気付いた。彼はこの現象が一貫して続いていたことに注目し、少なくとも次の10年間はこの傾向が続くと予測した。この予想は、『ムーアの法則』として知られるようになった。そこにレイ・カーツワイルが登場し、驚くべきことを見出した。コンピュータは、トランジスタが発明されるはるか以前から、同じペースで性能を倍増させてきていたという事実である。1890年に米国国勢調査で使用された単純な電気機械装置から始まり、コンピュータの処理能力をグラフ化してみると、基盤技術に関係なく、初めから処理能力は約2年ごとに倍増してきていたことが明らかになった。これは真に奇妙な現象である。コンピュータの基盤技術が機械式からリレー式、真空管、そして集積回路へと変遷してきたにもかかわらず、ムーアの法則が破られた瞬間は一度もなかった。何故だろうか?事実として、その答えを誰も知らない。コンピュータの速度を決定する処理能力が、なぜこの厳密な法則に従うのか。現時点では誰も真実を知らず、ほとんど仮説すら存在しない状況である。しかしながら、これが何らかの宇宙的法則である可能性は考えられている。特定の目標に到達するには一定量の技術が必要で、その技術が得られた後、その技術を使ってさらに技術を2倍にするといった仕組みであるかもしれない。しかし、ここからが真に興味深いところである。驚くべき事実として、「コンピュータだけでなくほとんど全ての技術が、それぞれに固有のムーアの法則に従っている」ということが明らかになっている。全ての技術の性能が必ずしも2年ごとに倍増するわけではないが、技術を支える要素の一部は確かに一定の年数ごとに倍増していると言えるであろう。『技術の倍加(2のべき乗)』という現象は、最初に抱く印象よりもかなり重大な話である。科学的方法とムーアの不思議な法則の組み合わせが、私たちの日常生活に不可欠な新技術の爆発的な発展をもたらした。ロボット工学、ナノテクノロジー、遺伝子編集技術、宇宙飛行、原子力など、さまざまな先端技術の進歩は驚異的である。実際、私たちがもはやその驚異に気づけないほどの速さで技術は進歩している。新技術が到来するスピードは速すぎて、ごく当たり前のことのように思えてしまう。
ところで、第三の時代の終わりに登場し、圧倒的な影響を及ぼした技術の一つは『コンピュータ』である。コンピュータは単なる道具ではなく、「深い哲学的意義を持つ装置」である。どういう意味なのか。コンピュータはたった1つの特異な機能、すなわち『計算』を行う。それは当たり前だが、「計算」は宇宙の心臓の拍動、宇宙の時計の秒針なのである。計算はあまりにも根本すぎて、もはや脳、宇宙、空間、時間、意識、生命そのもの、つまりあらゆるものが計算だと考える人もいる。博学者スティーブン・ウルフラムもそういった考えの持ち主で、2002年に出版した1200ページにも及ぶ大著『新しい種類の科学』(Stephen Wolfram “A New Kind of Science”, Wolfram Media Inc.)で自説を展開している。宇宙の多くは数式で表現可能である。ハリケーンやDNAは数式で記述でき、雪の結晶や砂丘も同様である。そして、この事実の素晴らしさは、物理世界で起きる物事のうち数式で表せるものは、切手サイズの計算機の中でモデル化できてしまうのである。例えば、人類を月まで運ぶには、ロケットやブーストや重力といった、物理世界の物事に関する気が遠くなるほど複雑な計算が必要だ。しかしそれは同時に、小さなプロセッサの中で0と1を並べればシミュレーション可能だということでもある。この事実が示唆する重要な真理とは、コンピュータでモデリングできる全ての物事は、現実世界でも数式に従って生じているということである。アポロ11号の打ち上げは数式で記述された。これは単に数式が用いられたという意味ではない。打ち上げそのものが数式に基づいていたということである。アポロ計画自体が数式に基づいていたのだ。この視点から考えると、「人間自身が数式で記述可能かどうか、私たちの心がアポロ11号が従ったのと同じ基本ルールに従う巨大な機械なのかどうかを問わざるを得ない」。コンピュータの限界(存在するのであれば)について理解しようとするならば、こういった問いに答える必要がある。その意味で、コンピュータは哲学的に重要な装置と言えるのである。ハンマーは単に釘を打つだけで、ノコギリは木を切るだけだが、コンピュータは物理世界の無数の現象を再現可能である。私たちはまだコンピュータの本質的な意味を十分に理解していないと言えるかもしれない。コンピュータが我々の世界を劇的に変えたということだけは確かだが、見かけ以上の変化が進行中である。著名な教授かつ哲学者であるマーシャル・マクルーハンは数十年前に次のように述べた。「コンピュータは人類史上最高の、技術で成り立った衣服であり、私たちの中枢神経系を拡張する装置だ。これに比べたら、車輪などはただのフラフープである」。コンピュータは新しいものでありながら既にあらゆるところに存在し、100年後どころか10年後のコンピュータが何をできるようになっているかも、想像するのが難しい。コンピュータはいったいどこから来たのだろうか。どういういきさつで私たちはこんなものが作れると思いつき、作ろうと決めたのだろうか。コンピュータの誕生から今日までの歴史はかなり短く、ここでの目的に照らせば、『バベッジ』、『チューリング』、『フォン・ノイマン』、『シャノン』という4人の名を挙げるだけで十分である。彼らの主要な功績を1つずつ紹介しまとめると、チャールズ・バベッジは「機械は計算できる」ということを示し、アラン・チューリングは「機械は計算だけでなくプログラムも実行できる」ことを示し、ジョン・フォン・ノイマンは「ハードウェアの組み立て方」を考案し、クロード・シャノンは「ソフトウェアを使えば一見数学的問題に見えないようなものも実行できる」ということを示した。私たちが現在いるのは、そういう状況である。
現在、『終わりを迎えつつある第三の時代から、第四の時代の入り口へ』という時代である。それぞれの時代において、私たちの先祖たちは身体機能や精神機能の一部を『技術でアウトソーシング』してきた。例えば、消化機能を助けるために『火』を使い、記憶力を拡張するために『文字』を使い、背中や足の負担を減らすために『車輪』を使い始めた、といった具合である。そして時代が進み、『機械仕掛けの脳』を生み出した。この装置は多才であり、我々が出すあらゆる問いを無限に解答することが可能になるようにプログラムされている。現在、私たちは、デバイスが自律的に機能するよう指導する手段、すなわち『人工知能(AI)』を開発しつつある。そして『ロボット』工学の力を借りて、『人工知能に、自ら動き、物理世界と相互作用する力を与え始めた』ところである。コンピュータとロボットの組み合わせにより、思考や行動をより多くアウトソースできるようになる可能性がある。これはものすごい変化である。この変化こそが、第四の、新たな時代の幕開けを告げる。しかし、この変化が私たちに突きつける問題は難解である。「ヒトであるとはどういう意味か」、ということに関わるからである。「機械は思考できるのか。機械は意識を持てるのか。人がやるあらゆることは、機械で再現可能なのか。実は私たちも機械なのか」。我々はすでに、新時代、第四の時代にいるのだろうか。しかし、ここで重要なのは、いつ第四の時代が始まったかではなく、一度その時代に入ったら最後、変化が急激に進行するということである。車輪の発明から月面着陸までには5000年かかった。しかし、その半分の時間が経過した2500年前に月到達まであと半分のところにいたわけではない。月面への到達はまだ遥か遠くにあった。音速を超える飛行が初めて成功したのは、月面着陸のわずか20年前のことであった。また、飛行機による初飛行は月面着陸の60年前であった。つまり、車輪の発明から4940年もの間、私たちは地上に張り付いて生活していたが、その後のわずか60年間で、私たちは飛行可能になり、さらに月まで行き来できるようになった。『私たちが直面している第四の変化は、これくらいのスピード感で、次々に起こる劇的かつ革新的なブレークスルーとともにやってくることが予想される』。そして、飛行機が着陸直前に最も揺れるように、これからの変化も大きな揺れを伴う可能性がある。おそらく、過去5000年間で起きたよりも多くの変化が、今後50年間で起きるだろう。ウラジーミル・レーニンがかつて言ったように、「10年間何も起こらないこともあれば、数週間で10年分の事象が起こることもある」のだ。
ところで、最新の技術である『人工知能』とはどのようなものだろうか。この技術について議論する人たちは、しばしば『狭いAI』と『広いAI』、つまり2つの全く異なる概念を考慮に入れている。しかし、現在のところ、実現している人工知能はすべて「狭いAI」であり、これは「弱いAI(weak AI)」とも呼ばれる。私たちはまだ、この種類の人工知能を構築する方法しか知らないのである。とは言うものの、狭いAIは驚くほど便利な存在でもある。狭いAIは、コンピュータに特定の問題を解決する能力、または特定のタスクを達成する能力を付与する。一方、「広いAI」は3つの呼び名があり、「一般的AI(general AI)」、「強いAI(strong AI)」、そして「汎用AI(artificial general intelligence(AGI))」と呼ばれる。これらの名称はどれも同じ意味を持つが、ここでは『AGI』を用いることにする。AGIは人間と同じような知能を持ち、何でも行うことができる人工知能である。現時点で、AGIは存在していない。どうやったらAGIを作れるのか、そもそもAGIを作ることが可能なのかについても、統一見解は得られていない。なお、「狭いAI」を作成するには大まかに分けて3つの手法、「モデルを作る」、「エキスパートに聞く」、「データから学ぶ(『機械学習』)」のいずれかが基本的な方法である。解決すべき課題に応じて最適なアプローチが決まるため、これらのいずれか一つがAIを作る「正しい」方法であるわけではない。ただ、この3つの手法はそれぞれがAIを作成する正当な方法であるものの、「AGI」という分野は全く異なるもので、その実現には全く新たなアプローチが必要となる可能性がある。すなわち、設定されていない課題も解くことが必要なAGIの設計は、特定の範囲の課題を解けばよいというAIの設計とは根本的に異なるものであるかもしれない。なお、AIにとって最も適した形状は、物理世界と直接関わりを持つことが可能な形状、すなわち『ロボット』であると考えられる。実際に、AIという技術は、自身に物理的な体が与えられ、外部環境とのインタラクションを通じて学習することができる状態にならなければ、ある一定のレベル以上に進化することが難しいと考えられている。優れたロボットを作成する技術は、新たな合金、高性能のバッテリー、高性能のセンサー、より効率的な移動方法の開発に伴い、やや進行が鈍いながらも着実に進化している。しかしながら、ロボティクスの分野が再び注目を集め始めたのは、これらの進歩そのものよりも、現在開発中の高性能AIとロボットを組み合わせることで、何か特別な事象が起こるのではないかという期待感からである。つまり、私たちの生活環境と相互作用が可能な『AIロボット』の実現が、我々の次の目標である。
限りなく広がる闇の中のかくもちっぽけな存在である地球にて、いくつかの人類の中で最後に唯一生き残った私たち『現生人類』は、一つの、危うくもしかし確固たるシステムの中で進化を遂げ、独自な文明を構築してきた。今や、『ロボットとAI』の時代に突入し、文明を支える技術の進化速度はますます加速しつつあり、さらに『汎用人工知能=私たち自らの存在をも左右しかねない自律システム』の実現に向けて取り組んでいる。私たちは人類史上最も重要な転換点に立っているのかもしれない。
参考文献
- 僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない この世で一番おもしろい宇宙入門
We Have No Idea A Guide to the Unknown Universe
著者:ジョージ・チャム Jorge Cham、ダニエル・ホワイトソン Daniel Whiteson
訳者:水谷淳(みずたに じゅん)
ダイヤモンド社 2018年11月7日 第1刷発行、2019年3月5日 第6刷発行
- 岩波新書(新赤版)543 生命と地球の歴史
著者:丸山茂徳(まるやま しげのり)、磯﨑行雄(いそざき ゆきお)
株式会社 岩波書店 2012年4月24日 第21刷発行
- 生命、エネルギー、進化
THE VITAL QUESTION Why Is Life the Way It Is?
著者:ニック・レーン Nick Lane
訳者:斉藤隆央(さいとう たかお)
株式会社 みすず書房 2016年9月13日 第1刷発行、2018年3月9日 第10刷発行
- 生物はなぜ誕生したのか ― 生命の起源と進化の最新科学
A NEW HISTORY OF LIFE
THE RADICAL NEW DISCOVERIES ABOUT THE ORIGINS AND EVOLUTION OF LIFE ON EARTH
著者:ピーター・ウォード Peter Ward, Ph.D.
ジョゼフ・カーシュヴィンク Joseph Kirschvink, Ph.D.
訳者:梶山あゆみ(かじやま あゆみ)
株式会社河出書房新社 2016年3月30日 3刷発行
- 生命進化の物理法則
THE EQUATIONS OF LIFE The Hidden Rules Shaping Evolution
著者:チャールズ・コケル Charles Cockell
訳者:藤原多伽夫(ふじわら たかお)
株式会社河出書房新社 2019年12月30日 初版発行
- 世界の起源 人類を決定づけた地球の歴史
ORIGINS How the Earth Made Us
著者:ルイス・ダートネル Lewis Dartnell
訳者:東郷えりか(とうごう えりか)
株式会社河出書房新社 2019年11月30日 初版発行
- 人類の歴史とAIの未来
THE FOURTH AGE
著者:バイロン・リース Byron Reese
訳者:小谷美央(ふるたに みお)
株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン 2019年4月30日 第1刷発行
- そろそろ、人工知能の真実を話そう
LE MYTHE DE SINGULARITE
著者:ジャン=ガブリエル・ガナシア Jean-Gabriel Ganascia
監訳者:伊藤直子(いとう なおこ)
訳者:小林重裕(こばやし しげひろ)他
株式会社 早川書房 2017年5月25日 初版発行